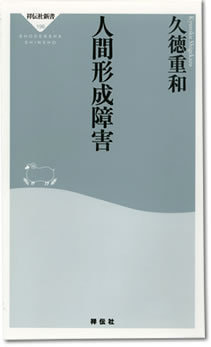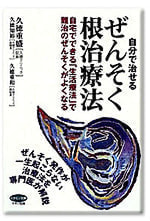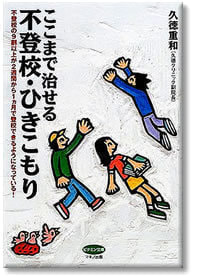■きゅうとく医院ってどんなところ?
きゅうとく医院は「生きるたくましさの診察」を専門としています
きゅうとく医院が考える「生きるたくましさ」とは
「生きるたくましさの診察」などというとなんだか奇妙に聞こえるかもしれませんが、動物が成長する過程は「生きるたくましさを身につける過程」でもあります。特に子育てをする動物ではこの事実は重要であり、その中でも特に甚だしいのが人間です。人間に近いゴリラやチンパンジーなどが3~4年で大人になるのに対して、人間は15年かけて「たくましい大人」に育っていかなくてはならないからです。
生まれた時には「親の顔も見分けられないような寝たきり状態」の赤ちゃんでも、3歳になったころには親と一緒に走り回れるような「身体機能のたくましさ」が備わってきます。さらに成長した10歳頃からは、思い切り動き回れる体を使って友達と張り合ったり揉めたりしながらも、人間関係をうまくこなしていくだけの「自我のたくましさ」も必要になります。そして15歳になった時には、かつての集団就職児のように、いざとなったら親元を離れて一人でも暮らしていくことができるような自我のたくましさも備わっていなければなりません。
この身体機能のたくましさと自我のたくましさが「社会の中でうまく生きていく力」の基礎になります。人間は日々の暮らしの中でのいろいろなトラブルに対してこの二つのたくましさを使いこなして、家族や仲間とともに困難を乗り越え「いろいろあってもうまく生きていく」ことができるように成長していく生き物なのです。
この「うまく生きていく力」が「社会の中に居場所を作って心身ともに健康に生きていく力」であり「生きるたくましさ」といえます。きゅうとく医院はこの「生きるたくましさ」がどのように作られていくのかを研究し診察することを最も専門としています。
「身体機能のたくましさ」は成長とともに充実していきます
生まれた時には寝たきり状態であった赤ちゃんでも、成長につれて身体機能が充実して活動性が増していきます。この活動性の充実を支える基本機能としては「呼吸機能、循環機能、消化機能、皮膚のバリア機能、免疫機能」の五つが最も重要になります。
これらの機能は循環機能を除けば妊娠中は全く働いておらず、生まれた時でも生命維持のための最低限レベルでしか働いていません。しかし生まれた後には目覚ましい勢いでその機能を充実させていきます。
呼吸機能を充実させることにより「しっかりと呼吸ができる」気管支ができあがり、循環機能を充実させることにより「全身に血液を循環させる」心臓ができあがります。消化機能を充実させれば「自前でエネルギー補給ができる」ようになり、皮膚のバリア機能を充実させれば「しっとりとして乾燥に耐え異物や病原菌から体を守る」皮膚になります。そして免疫を充実させれば「病原菌を抑え込みアレルギー体質から抜け出していく」ように育っていくのです。
このようにして新生児は「身体機能のたくましさ」を充実させることによって「思い切り動き回れる体」を築きあげながら、幼児から少年、青年へと成長していくのです。
これらの身体機能を充実させるために備わっている体内システムがアドレナリンとステロイドなどの「副腎・交感神経系ホルモン」です。これらのホルモンは「闘争と逃走のホルモン」とも呼ばれていて、たとえば命がけで戦う時とか必死で逃げる時などに、体を「思いきり動き回れる状態に変化させる」働きを持っています。
この二つのホルモンは赤ちゃんが首が座って寝返りを打ち始める(つまり赤ちゃんが自分の意思で動き始める)ころから本格的に働き始めて、3歳から6歳にかけて五つの身体機能をどんどん充実させていきます。ですからこの時期にはこれらのホルモンがしっかり分泌されてどんどん活性化されて、働かされて、身体機能のたくましさが「ぐいぐいと伸ばされていく」ような生活を送らせることが極めて重要になります。屋外での活発な生活が多いこと、温度変化(特に寒さ)に耐えること、よく気が付いてやる気があること、自信があって大胆なことなどは特に大切な要素になります。
これらのホルモンが十分に充実して3歳ごろまでに「思い切り動き回れる体」ができ上がった時には、喘息やアトピー性皮膚炎には「なりたくてもなれない」体質ができ上がります。反対に十分に充実せずに成長してしまうと、五つの身体機能が不安定になる体質ができてしまいます。その結果として発生する疾患の代表的なものが、呼吸機能であれば気管支喘息であり、循環機能であれば起立性調節障害、消化機能であれば過敏性腸症候群、皮膚のバリア機能障害であればアトピー性皮膚炎、免疫機能であればアレルギー性疾患ということになります。
これらの疾患では共通して「思い切り動き回ることを妨げる」症状が現れます。喘息では呼吸が苦しくなって動けなくなり、起立性低血圧では血圧が下がって動けなくなります。過敏性腸症候群では便意が行動を制限し栄養不足になり体力を消耗します。アトピー性皮膚炎では皮膚の炎症や細菌感染が頻発します。スギ花粉症では屋外での活動が妨げられますし、食物アレルギーであれば仲間と同じ食物が食べられなくなります。
そしてこれらの疾患ではアドレナリン系およびステロイド系の薬を内服・吸入・外用などで体外から補うことにより症状が改善します。この事実からもアドレナリンとステロイドの「体内での活性化不足」がこれらの疾患に共通した原因であることがわかります。
「自我のたくましさ」も成長の中で作られていきます。
「自我」とは、周りと関わり合いながら今を生きている自分自身の「思考と感情と意思と行動の働きのすべて」を指します。つまりその人の「人柄」であり「生きる姿勢」ともいえます。
自我は1歳ごろから芽生え始め、その後の周囲との人間関係を通して作られていきます。そして思春期ごろにはその人固有の形で確立されます。ですから「物心がついてから今までの周囲(家族・友人・近隣・社会)との心理的な相互作用の結晶体」がその人の自我であるということになります。
そしてこの自我はその人の「思考と感情と意思と行動」を無意識レベルから操作して、その人の「日常生活内での言動」を自動的に設定して行動化します。これが周りから「性格」とか「人柄」などとも呼ばれる、その人の「生きる姿勢」になります。
自我が健全であるほどその人の生きる姿勢も自動的に健全なものになり、日常的なトラブル程度には振り回されることもなく心身ともに安定して暮らせるようになります。更にはこの健全な自我は自動的に健全な人間関係を紡ぎ出し、10歳から思春期頃にかけて家族や仲間と快適に生活できる「居場所」を作り上げる力も伸ばしてくれます。
そしてこの健全な自我が、同時期までに築き上げてきた「思い切り動き回れる体」と協調して働くことにより「物事に挑戦する力」、「世の中に打って出る力」を発揮できるようになっていきます。これが様々なトラブルに対応してたくましく生きていく「頼もしい大人に成長した」ということであり、昔であれば「元服を迎えた」ということになります。
反対に自我のたくましさに何らかの問題があった場合には、健全な人間関係を紡ぎ出すことが難しくなることも起こり得ます。その場合には、「何故だかわからないが人の目が気になる」とか「日常の人付き合いに緊張する・疲れる」、「思い通りにならないとどうすればよいのかわからなくなる」、「何故だかわからないがうまく生きていくことが難しくて疲れる」などという、「社会の中に居場所を作って快適に暮らしていくことが難しい状態」が自動的に現れてくることになります。
「人間形成医学」という考え方
ここまでお話ししてきましたように、人間の「心身両面の生きるたくましさ」とか「人生に挑戦する力」の大部分は生まれた後の「毎日の生活」の中で作り上げられるものなのです。ですから生まれ落ちた新生児が、毎日をどのように暮らしてどのように成長すれば健全な身体機能と自我が出来上がっていくのか?を知ることは健康な人生を送るための非常に役立つ情報になります。この人間のたくましさの形成について研究する医学を私たちは「人間形成医学」と呼んでいます。
人間形成医学は「人間の心身の成長(=自我形成と体質形成)を研究する医学」であり「人間の心身の成長を診察する医学」ということもできます。この立場に立つことにより、従来根治させることが難しいとされていた、気管支喘息やアトピー性皮膚炎、不登校、起立性調節障害、引きこもり、適応障害、パーソナリティ障害などを根本的に改善させて薬を中止することもそれほど難しくはなくなりました。
これらの疾患では薬による治療では症状を抑えることしかできませんが、患者さんの「生きる姿勢・生きるたくましさ」までに目を向けた治療を行えば症状は自動的に改善に向かうからです。
そしてすでにお話ししましたように、「生きるたくましさ」は、「幼少期からの毎日の生活」によって作られますから、それを治療するということは「患者さんの毎日の生活を治療する」ことにほかなりません。
私たちはこの考え方に基づいた治療法を「生活療法」と呼んでいます。生活療法は患者さんの生活習慣を心身両面から調整することにより、患者さんの心身の「生きるたくましさ」を整えて、症状を取り去り薬も中止することを目指す治療法といえます。
専門領域の疾患と治療法
以上のような考え方によって、きゅうとく医院では次のような分野の治療を専門としています。
最も専門とする疾患
- 気管支喘息(小児・成人)/喘息類縁疾患の過敏性肺炎・好酸球性肺炎・肺アスペルギルス症・アレルギー性肉芽腫性血管炎/肺気腫などの慢性閉塞性肺疾患(COPD)/長引く咳/咳喘息・アトピー咳嗽/スギ花粉症・食物アレルギーなどのアレルギー性疾患
- 起立性調節障害/過呼吸症候群/過敏性腸症候群/慢性蕁麻疹/夜尿症・遺尿症などの心身症
- 不登校/ひきこもり/新型うつ/適応障害/不安障害・気分障害・パーソナリティ障害・強迫性障害・職場でのメンタルヘルスなどの、「毎日の生活や人間関係がうまくいかなくて生き辛い」状態
- 乳幼児期の「人間関係がうまくいかない」状態:愛着障害/過度に落ち着きがな/強い人見知り/過度の神経質/無気力/自宅以外では言葉が出ないなどの問題
最も専門とする治療法
- 小児・成人の喘息:吸入ステロイドからの離脱と根治を目指す「総合根本療法」
- 咳喘息への「総合根本療法」
- 肺気腫などの慢性閉塞性肺疾患(COPD)と在宅酸素療法(HOT)の管理
- 減感作療法(注射法・SCIT):スギ、ダニ、イネ科花粉5種類(自費)、イヌ(自費)、ネコ(自費)など
- 舌下免疫療法(SLIT):スギ(シダキュア)、ダニ(ミティキュア)
- 食物アレルギーの負荷試験と経口的減感作療法
- 蜂アレルギーの急速減感作療法(現在は治療エキス輸入停止のため実施していません)
- 起立性調節障害、不登校やひきこもりなどの社会参加の力(=居場所を作る力)を伸ばすための生活療法
- パーソナリティ障害、社会不安障害、職場でのメンタルヘルス不調などに対する生活療法
- 乳幼児を「凛々しく生き生きとした腕白・お転婆」に成長させるための生活療法・育児相談
「生活療法」の基本的な考え方
もともと生活療法は「不安をコントロールする」ことにより小児喘息の重症化を防ぐために考案された治療法です。そしてこの不安をコントロールする機能が喘息のみならず不登校や引きこもり、適応障害などの改善にも優れた効果を発揮することが分かってきました。
気管支喘息と不登校やひきこもりなどは全く別の領域の疾患だと思われていますが、実は両者は根底の部分で「たくましさ」と「不安」というキーワードで繋がっているのです。
生活療法で医師が行う仕事は、一人一人の患者さんについて、「あなたの喘息はこうすれば治せます」とか「子どもさんの不登校はこうすればよくなります」、「こうすれば人間関係に悩まなくてもすむようになります」などという状態に向かうように「患者さんの生活習慣を調整する」ことにあります。
治療にあたっては、患者さんの当面の生活方針を「このように生活を修正すれば症状は必ず改善に向かう」という内容に設定します。このように設定した生活方針を私たちは「健全生活」と呼んでいます。この健全生活の設定を行うことが、医師が行う一つ目の重要な仕事になります。
そしてこの健全生活の設定が適切であれば、あとはそれを励行することにより症状は自動的に改善していきます。この関係はたとえば糖尿病であれば「運動と適正体重」が症状を改善させ、高血圧であれば「運動と減塩」が症状を改善させる関係に似ています。
生活療法は効果が現れるのも比較的速やかで、治療開始後2~3カ月で症状は改善に向かい始めますが、治療開始後に様々な理由で健全生活の励行が難しくなることも珍しくはありません。このような場合にその原因を見つけ出して対策を提案して助言することが、医師が行う二つ目の重要な仕事になります。
きゅうとく医院では、生活療法はもともと患者さんに備わっている自然治癒力を活性化して、「患者さんの身体機能と自我のたくましさを充実させる治療法]であると考えています。ですから生活療法は「患者さんの内面的変化を促す治療法」でもあり認知行動療法の応用ということになります。
生活療法の詳細につきましては、『専門外来のクリニックポリシー』、『生活療法の進め方』などをご覧下さい。
一般外来診察
一般外来診察
かかりつけ医として、内科、小児科、呼吸器科、アレルギー科の一般診療を行っています。
名古屋市医師会の病診連携システムにより、愛知医科大学、東名古屋病院、名古屋市立東部医療センター、日本赤十字病院、中部労災病院などと連携し専門外の疾患にも対応できる体制を取っています 。
予防接種 (予約制)
予防接種 (予約制)
各種予防接種(四種混合、二種混合、麻疹・風疹混合ワクチン、日本脳炎、肺炎球菌ワクチン、おたふくかぜ、水痘、インフルエンザワクチン、コロナワクチンなど)を行っています。アレルギー体質の方への接種にも対応しています。詳しくは窓口へお問い合わせください
人間形成障害
この人間形成障害型の社会では、親がまったく普通の子育てをしているつもりであっても、子供たちに様々な問題が「予測もできない状況で自動的に」現れてくるようになります。
ぜんそくは自分で治せる
気管支ぜんそくの臨床は、いままでの『わからない・治らない』という時代から『原因を分析し実行すれば治る』時代に入ったのです...」。
ぜんそく根治療法
通院できない患者さんであっても、自宅で総合根本療法を実行して喘息を治していくことができるだけの知識を執筆されています。
ここまで治せる
不登校 ひきこもり
不登校をご家庭で「治す」ことも「予防する」ことも十分に可能です。不登校の解決は決して難しいものではないのです。