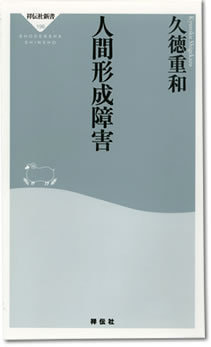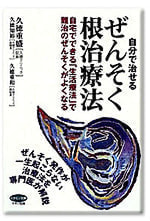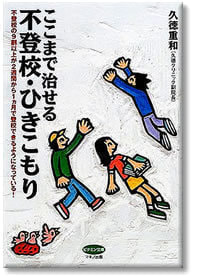疾患別のご案内
起立性調節障害(Orthostatic Disturbance:OD)
1.全般的な解説
起立性調障害(OD)は起立時や体動時に血圧調整機能が不安定になり日常生活が制限される疾患です。起立時にめまいや立ちくらみなどが現われるのが代表的な症状ですが、それ以外の日常生活の場でも全身倦怠感や動悸、気分不良などの低血圧症状が現われることも少なくありません。症状の強さはごく軽いものから日常生活に支障が出るものまでの幅があります。
我が国のODの研究は昭和38年に日本大学の大國真彦先生により始められました。それまでは虚弱児とか体質性の反応とみなされてあまり問題視されていなかったODが、海外では研究が進んでいることを知った大國先生が研究班を立ち上げて研究が始まりました。
ODが広く知られるようになったきっかけは、昭和50年代後半の「朝礼で倒れる子供たち」の出現です。そして同時期から増加し始めた不登校と連動するようにODも増加していきました。10歳前後から発症しやすく社会的活動性までが低下する点においてODと不登校との間には共通性が認められ、初期のころからODは不登校との関連についていろいろと研究されてきました。社会環境・生活環境と子どもの心身の成長・発達との関わりとか、心身症的側面などの観点からも研究されています。
自律神経機能の不安定さが症状の直接の原因であるため機能性の身体疾患ということもできますが、心理的ストレスの影響を受けやすく、50~60%に不登校を伴うという事実などから心身症とも位置付けられています。日本小児心身医学会のガイドラインでも「ODの70~80%は心身症として診療した方がよい」とされています。心理的要因として不安や無気力などの性格傾向も関与しますが、決して本人が「怠けている」訳ではありませんからその点については配慮が必要とされます。
自律神経の不安定さが原因になって血圧が低下して身体的活動性が損なわれ、ストレスの影響でも悪化するという反応性は、自律神経の不安定さが原因になって呼吸困難が現れストレスでも悪化して身体活動性が損なわれるという喘息発作と類似した反応ともいえます。このような理由でODを管支喘息の類縁疾患と捉える考え方もあります。久徳クリニックでの調査でもダニアレルギー強陽性の小児喘息患児63人中42人(66.7%)が後述の起立試験(schellong test)陽性でODの併発が認められました。
ODの背景には小心臓(small heart)などの身体的要因も関わっていることがわかっています。小心臓は胸部レントゲン撮影で診断できます。「心胸郭比」という項目の値が0.4以下で小心臓と診断されますが、小心臓になると心臓の血液循環機能の余力が少なくなるためODを起こしやすくなると考えられています。OD児での小心臓の出現率は健常児の8倍ほどになります。
2.検査・診断法
起立試験によって起立後の血圧低下が確認されれば確定診断になりますが、現実には起立試験の陽性率はあまり高くありません。大國先生の診断基準でも起立試験の所見は主要所見である「大症状」には含まれず、随伴症状の「小症状」に分類されています。後述の「新起立試験」でも陽性率は50%程度ですから、診断は本人の訴えと生活状態を参考にして下されることが多くなります。
(1)大國による診断基準
大國先生により昭和30年代に提案された診断基準です。平成18年(2006年)に小児心身医学会のガイドラインができるまでは国内で唯一の診断基準であり、この基準に基づいて治療が行われていました。現在では「旧基準」と呼ばれることもありますが、内容的にはまだ十分に活用できるものであり、きゅうとく医院では現在でもこの基準を使用しています。
この基準は問診と起立試験(schellong test)の結果から診断を下します。問診・検査項目は次のような「大症状」と「小症状」に分けられています。
大症状
- 立ちくらみ、あるいはめまいを起こし易い。
- 立っていると気持ちが悪くなる。ひどいと倒れる。
- 入浴時、あるいはいやなことを見聞きすると気持ちが悪くなる。
- 少し動くと動悸、または、息切れがする。
- 朝起きが悪い。
小症状
- 顔色が青白い。
- 食欲不振(少食)。
- 強い腹痛を時々訴える。
- 疲れ易い。
- 頭痛をしばしば訴える。
- 乗り物に酔う。
- 起立試験で脈圧狭小化16mmHg以上。
- 起立試験で収縮期血圧低下21mmHg以上。
- 起立試験で脈拍数増加1分21以上。
- 起立試験で立位心電図のTⅡの0.2mV以上の減高。その他の変化。
判定基準は、 a)大症状が1に小症状が3、b)大症状が2に小症状もある、c)大症状が3つ以上ある、のいずれかに該当した場合に「陽性」と判定されます。
(2)日本小児心身医学会「小児起立性調節障害診療ガイドライン改訂第3版(2023)」による診断基準
日本小児心身医学会の診療ガイドライン作成ワーキンググループ(WG)により作成されたガイドラインです。「一般小児科医向け」と「専門医向け」の2種類が作成されています。一般医向けは2006年に第1版が発行され2023年に改訂第3版が発行されています。専門医向けは2011年に発行されています。
このガイドラインの一番の特徴は大國先生の起立試験(schellong test)に「起立後血圧回復時間測定」という検査項目を加えた「新起立試験法」を行う点と、ODを4つのサブタイプに分類したところにあります。
診療にあたっては次の問診事項が3つ以上当てはまるか、2つであってもODが強く疑われる場合に診断を開始するとされています。問診項目は大國先生のものがそのまま引用されています。
- 立ちくらみ、あるいはめまいを起こしやすい。
- 立っていると気持ちが悪くなる。ひどくなると倒れる。
- 入浴時あるいはいやなことを見聞きすると気持ちが悪くなる。
- 少し動くと動悸あるいは息切れがする。
- 朝なかなか起きられず午前中調子が悪い。
- 顔色が青白い。
- 食欲不振。
- 臍疝痛(おへそ周りの急な腹痛)を時々訴える。
- 倦怠あるいは疲れやすい。
- 頭痛をしばしば訴える。
- 乗り物に酔いやすい。
上記に加えて次の症状のうち4つ以上が週1~2回以上みられる場合には、「心身症としてのOD」とも診断されます。
- 学校を休むと症状が軽減する。
- 身体症状が再発・再燃を繰り返す。
- 気にかかっていることを言われたりすると症状が増悪する。
- 1日のうちでも身体症状の程度が変化する。
- 身体的訴えが2つ以上にわたる。
- 日によって身体症状が次から次へと変化する。
問診によってODが疑われた場合には、新起立試験を行いODを次の1.から4.のサブタイプに分類し、5.の日常生活状態と合わせて身体的重症度を決定することになります。
しかしながらすでにお話ししましたように新起立試験の陽性率は50%程度ですから、約半数の患者さんは5.の「日常生活状況」によって重症度が決められることになります。各サブタイプの重症度に関しては「明確な線引きが難しくまだエビデンス(医学的根拠)はない」とされています。
- 起立直後性低血圧(Instantaneous orthostatic hypotension:INOH)
起立直後に血圧が低下しその後回復するかそのまま継続するタイプ。新起立試験陽性例の35~46%を占める。「血圧回復までに25秒以上かかるか、20秒以上かかりかつ60%以上の血圧低下」で陽性、「起立3~7分後にも収縮期血圧が15%以上低下する」で重症。 - 体位性頻脈症候群(Postural tachycardia syndrome:POTS)
血圧の低下は少ないが心拍数が上昇するタイプ。新起立試験陽性例の42~63%を占める。
「起立3分後以降に心拍数115以上または35以上の増加」で陽性、「起立後心拍数125以上または45以上の増加」で重症。 - 遷延性起立性低血圧(Delayed orthostatic hypotension:DeOH)
低下した血圧が回復せず継続するタイプ。新起立試験陽性例の3~10%を占める。「起立3分後以降に15%以上の収縮期血圧低下」で陽性。重症度基準は定められていない。 - 血管迷走神経性失神(Vaso-vagal syncope:VVS)
起立中に血圧が低下し気分不良から意識低下や意識消失がみられるタイプ。新起立試験陽性例の2~5%を占める。「INOHまたはPOTSを伴う」で重症。 - 症状や日常生活状況
軽症:時に症状があるが日常生活への影響は少ない。 中等症:午前中に症状が強くしばしば日常生活に支障があり、週に1~2回遅刻や欠席がみられる。 重症:強い症状のためほとんど毎日日常生活・学校生活に支障をきたす。
3.治療
(1) 日本小児心身医学会のガイドラインによる治療
日本小児心身医学会のOD診療ガイドラインは「一般向け」と「専門医向け」の2種類が作成されています。一般向けのガイドラインは「中等症までのODを一般の小児科医師が診察する場合の治療指針」が示されています。ODは比較的頻度の高い疾患(問診による陽性率は中高生で20%前後)ですから、一般小児科の先生方にもOD診療の基本を理解していただくことが一般向けガイドラインの作成目的とされています。
一般向けガイドラインによる治療では、まずは病状について十分な説明を行ったうえで「非薬物的療法」を行います。非薬物的療法とは、ODバンドや着圧ソックスなどの装具の利用、ゆっくり立ち上がるなどの「身体操作」を心がけ、日中もなるべく横にならない、体調のいいときはなるべく動く、水分と食塩の十分な補給(水分は1日2リットル、食塩は1日10g)、生活リズムを整えるなどの生活習慣の調整が推奨されています。
他に薬物療法、学校との連携、生活指導などが取り上げられていますが、基本的にはODを「身体疾患」と考えて、「まずは生物学的(=身体的)機能に焦点を当てた治療を優先」して、原則として心理療法は行わず、保護者に対しては「必ず回復するので心配しすぎないように、悲観的にならないようにと繰り返し励ます」ことが効果的であるとされています。当面4週間はこのガイドラインに沿って治療を行い、4週間経過しても効果が現れない場合などは専門医に紹介すると定められています。
専門医向けガイドラインは、一般向けガイドラインで4週間以上の治療を行っても改善しない患者さん、初診時に既に1ヵ月以上の不登校が続いている患者さん、精神科に通院しているが身体症状が持続している患者さんと、一般向けガイドラインでの身体的重症度が「重傷」の患者さんが治療対象になります。
専門医向けガイドラインでは、多職種が連携したうえでの、疾病教育・生活指導・心理療法・家族療法・認知行動療法などを取り入れた総合的な治療の指針が示されているのですが、もともとガイドラインはODについては「包括するとODについての基礎研究や本邦の診断基準に従った大規模な研究報告はなく、病態の全貌は解明されていない」、「国内での研究報告も少なくエビデンスも少ない」との立場に立っています。
病態が解明されていなければ効果的な(エビデンスのある)治療法を示すことはできませんから、ガイドラインは「エビデンスのある治療法」を示すことは目標とせず、「海外の文献と、WG関係医療機関、教育委員会、患者さんの家族会などからの広く様々な情報や意見を収集して検証し、ODに関連する幅広い情報の提供と診療の指針を示す」ことを目的として作成されています。
「本ガイドラインはあくまでも診療の参考に作成されており、必ずしもこれに従う必要はない」がガイドラインに明記された基本姿勢といえます。現実の治療現場においては、ガイドライン制定前から独自の治療法でODを改善させている先生方も決して少なくはありません。これらの先生方の独自の治療法もガイドラインは否定していないことになります。
ガイドラインによる治療成績は、一般向け・専門医向けをまとめて、思春期発症のPOTSでは治療開始後5~6年で85%までは無症状になり、中等症ODの1年後の回復率は約50%、2~3年後で70~80%とされています。不登校を伴う重症例では1年後の復学率は30%であり、社会復帰に少なくとも2~3年はかかると報告されています。
(2) ガイドラインについてのきゅうとく医院の考え (この項目はきゅうとく医院院長の個人的な見解です)。
以上述べてきたようにガイドラインは、「ODに関連する幅広い情報の提供と診療の指針を示す」ことを目的として作成されています。ですからガイドラインではODのメカニズムとかサブタイプ、基本的な治療姿勢」などについては非常に詳しく説明されています。多くの専門外の先生方からも「ODの様々な面からの理解に役に立つ」と高く評価されています。
しかし実際の治療に際しては幅広く詳細な診療指針の整理が今一つ不明確で手探りのような実効性の不確定な治療になってしまっている印象が強く感じられます。例えば一つの例として、一般向けガイドラインでは、「子供は必ず回復するので心配しすぎないように」と保護者を繰り返し励ますことが効果的としながらも、専門医向けのガイドラインでは「治療には平均的に2~3年かかり数年以上の長期に及ぶ場合もある」、「思春期症例の医療面接の第一目標は現状維持」、「不登校を伴う重症例では1年後の復学率は30%であり、社会復帰に少なくとも2~3年はかかる」とされているのは何だか整合性に欠けるといわざるを得ません。
それでもこのガイドラインは公的な学会が作成したものですから、様々な医療機関や関連団体が引用してWEB上でも広く紹介されています。ほとんどの引用先では一般向けのガイドラインがほぼそのまま引用されているようですが、治療開始後4週間で改善しない場合などの「専門医への紹介基準」までを省略せずに記載している引用先は少ないようです。
その結果一般向けガイドラインが「OD治療の全て」の様に誤解された形でWEB上で広がり、「ODはよくわからないし治しにくいから様子を見るしかない」という不安やあきらめのような認識が近年広まりつつあるように感じられます。これは憂慮すべき状況であるといえます。
またこの不安を逆手にとってサプリメントとか整体などに誘導するサイトも急増しています。これらのサイトに対しては小児心身医学会が厳重な抗議声明を発しています。
(3) きゅうとく医院のOD(不登校を伴う)治療の考え方
きゅうとく医院の前身である久徳クリニックでは昭和54年から不登校への生活療法を実施していました。当時ODはそれほど重要視されていませんでしたが、昭和59年の調査では小学校から大学生までの不登校児304人中97人(31.9%)が大國先生の基準でOD陽性であり、昭和61年の不登校児714人の調査では陽性率は84.5%でした。「朝礼で倒れる子供たち」が現れ始めた昭和50年代後半からODが激増してきたことがわかります。
久徳クリニックの外来でも「ODを伴う不登校」の患者さんが激増しましたが、基本的にはそれまで行ってきた生活療法で十分に治療可能でした。昭和59年の調査では、ODの有無に関わらず「問題なく登校できる」レベルまでの登校再開率は95.7%に達していました。
ODがあったとしても、立ちくらみとか倦怠感などの症状が軽微であり日常生活への影響も少ない状態(軽症)であれば鍛錬と多少の薬物療法の併用で対応できますから、専門医までを受診する必要はないといえます。
ODが切実な問題になるのはやはり不登校と併発した時になります。きゅうとく医院では不登校を伴うODに対しても喘息や不登校と同様に生活療法を実施しています。
その理由は既にお話ししましたように、ODを伴う不登校であっても生活療法で十分に対応できるという結果が得られているということと、「きゅうとく医院ってどんなところ?」でもお話ししましたように、ODも喘息や不登校と同じように、「生きるたくましさの充実不足」と考えることができるからです。
また文部科学省の調査では不登校の原因の約半数は「無気力」とされています。無気力でもODに類似した身体症状が現れますから、「問診ではODと診断されたが起立試験は陰性」という患者さんの場合には、問題の本質が「無気力性の不登校か起立試験陰性のODか」の鑑別が必要になります。これがなかなか難しくて時間ばかりを費やして鑑別に至らないことも珍しくはありません。
ですからきゅうとく医院ではODと不登校が併発している場合には、原則として「ODを伴った不登校」として治療を行っています。基本的な治療方針は「ODにも配慮した形での生活療法」になります。平成30年に受診された32名の「不登校を伴うODの患者さん」の調査では、平成31年4月の時点で70%までの患者さんが登校可能になっていました。平成20年に調査した不登校の登校再開率は2~3ヶ月で67%でしたから、ほぼ同等の改善度といえます。ODがあるから不登校が改善しにくいということではないときゅうとく医院では考えています。生活療法につきましては「専門外来のクリニックポリシー」もご覧ください。
人間形成障害
この人間形成障害型の社会では、親がまったく普通の子育てをしているつもりであっても、子供たちに様々な問題が「予測もできない状況で自動的に」現れてくるようになります。
ぜんそくは自分で治せる
気管支ぜんそくの臨床は、いままでの『わからない・治らない』という時代から『原因を分析し実行すれば治る』時代に入ったのです...」。
ぜんそく根治療法
通院できない患者さんであっても、自宅で総合根本療法を実行して喘息を治していくことができるだけの知識を執筆されています。
ここまで治せる
不登校 ひきこもり
不登校をご家庭で「治す」ことも「予防する」ことも十分に可能です。不登校の解決は決して難しいものではないのです。