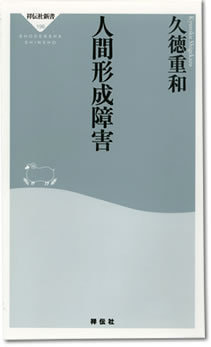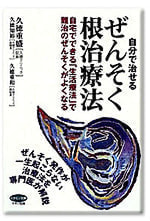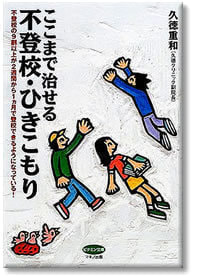疾患別のご案内
不登校
〜 不登校についてのきゅうとく医院の考え方 〜
1. 昭和50年代以降の我が国の不登校対策の経緯
昭和50年代から社会問題化してきた不登校に対して昭和63年に文部科学省は「不登校の背景には教師の権力的締め付けがある」と指摘し、平成4年には「不登校はどの子にも起こりうる。強い登校刺激は不登校をかえって悪化させるので、子どものエネルギーがたまるまで待つべきである」と提言しました。その結果「登校刺激を与えずに見守る」という対応が一般化して全国的に定着しました。
そして約10年後の平成13年に文部科学省が「不登校に対する実態調査」を行いました。これは初めての大掛かりな実態調査であり、不登校のままで中学校を卒業した子どもたちが20歳になった時の生活状況を調べたものです。その結果は概ね次のようなものでした。
就学15.6%、就労48.8%、就学と就労12.8%、就学・就労ともにせず22.8%。主な就学先は高校6.5%、専修・各種学校8.0%、短大・大学8.5%であり、就労の内訳は正社員22.3%、フルタイムの家業手伝い3.6%などでした。
アンケートの回答率も5%程度と低く、まとめてみれば「全体の5割以上がニートかフリーターで、そのうちの約3分の1がひきこもり」と推測される状況だったのです。
その結果を受けて文部科学省は平成4年の提言を大きく転換しました。
平成15年3月に「不登校は見守るだけでは解決しない。ただ待つだけではなく状況に応じて登校への働きかけを行い社会的な自立を目指すべきである」と指導方針を180度変更したのです。そしてスクールカウンセラーなどを配置して指導体制の充実を図りました。
しかしその後も状況は好転しませんでした。
平成26年に13年ぶり2回目の実態調査の結果が発表されました。この調査では平成18年に不登校のままで中学校を卒業した子どもたちが20歳になった時の生活状況が報告されています。
ここでも詳細は割愛しますが、アンケート回答率は3.9%と低く、まとめてみれば「全体の6割弱がニートかフリーターで、そのうちの約3分の1がひきこもり」と推測される状況でした。平成13年の調査とほとんど変わりがなかったのです。
そして全国の不登校児は平成15年は12万6千人、平成26年では12万2千人と全く減少しておらず、平成22年ごろからは「8050問題」のような深刻な問題も現れてきました。
文部科学省は平成15年の提言の時点で「不登校に対して教育課題として対応するのには限界がある」との(弱気な?)見解を示し、平成17年頃から「フリースクールへの通所を正式な義務教育の登校とみなすか?」との検討を始めていました。そして平成28年に「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(教育機会確保法)」を施行しました。
この法律で文部科学省は不登校対策を歴史的といってもよいほど大きく転換しています。
まずは平成4年の「エネルギーがたまるまで待つ」とか平成15年の「ただ待つのではなく早期の対応を行うべき」などの提言をすべて廃止しました。それまでの(あまり効果はなかったにしろ)「不登校児を学校に復帰させる」ことを目指していた提言をすべて撤廃してしまったのです。
そして「不登校児への支援については、学校へ登校するという結果のみを目標にするのではなく児童生徒の希望を尊重して状態に応じて行われるべきである」として、「学校以外の教育の場の活用も必要であり、不登校特例校などの設置の促進と多様な教育機会を提供している民間団体との連携と協力を積極的に推進する」としています。
簡単にまとめれば「学校以外の場所での勉強でも登校と同等に扱うので学校に戻ることを重要視する必要はない」ということになります。もう少し砕けた(意地悪な?)表現をしてしまえば「私たち(文部科学省)ではもうどうしようもありませんから、今後の不登校への対応は民間団体にもお任せします(連携と協力)。フリースクールなどで勉強してもらえれば登校は免除します。無理して学校へ戻ることはありません」という方針を文部科学省が積極的に推進することになったといえます。「不登校への対応を民間業者に外注する」ということであり、まさに「歴史的な大転換」ということになります。
その結果不登校児は一気に増加しました。小中学校の不登校児は平成10年に10万人を突破していますが、その後は大きく増加することもなく平成28年までは12~13万人ぐらいで落ち着いていました。しかし平成28年の法律施行後には、平成29年14万4千人、同30年16万4千人、令和元年18万1千人、同2年19万6千人、同3年24万4千人、同4年29万6千人と激増しています。
2.不登校についてのきゅうとく医院の考え方
(1)不登校にもいろいろある
文部科学省の定義によれば「不登校とは何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくてもできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いた者」とされています。ここでいう「病気」とは一人での移動や外出も困難な深刻な身体疾患が想定されています。発達障害やADHDなどは最近では「病気というよりも心理面での個性」という捉え方になってきており、不登校の定義にある「病気」には該当しないという考え方が主流になってきました。
不登校の中でも明らかないじめや暴力行為があって「登校を考えるだけでも死にたくなってしまう」ような場合や、親子関係に問題があって本人が絶望に至っているような場合などでは、登校を促すことは過酷すぎますから適切ではありません。このようなケースでは「無理して学校に戻ることはない」という選択も間違いではありません。
また発達障害などが原因で不登校になっている場合には、不登校の治療よりも元の問題の治療が優先されます。元の問題が落ち着けば不登校が自然に改善していくことも珍しくありません。このような基礎疾患があるケースはもともと不登校と考えるべきではなかったともいえます。
いずれにしろ不登校の要因にはいじめを含んだ学校での人間関係、親子関係、虐待やネグレクト、暴力問題、発達障害、その他本人側の問題、など「いろいろある」ということになります。
令和2年度の文部科学省の調査では、小中学校の不登校で「学校側に原因があった」例は22.7%で、そのうちの16.5 %が「教師・部活なども含む人間関係」が原因とされています。「いじめ」は0.2%でした。最も多かったものは「無気力や不安」であり全体の46.9%を占めていました。
この無気力や不安が原因になっている不登校の中には「学校に問題はない、自分は学校に行きたい、しかし登校できない」という形のものも少なくありません。この形の不登校に対してまで「無理して登校することはない」としてしまうのには問題があります。この対応は「学校に行きたい」という本人の希望について配慮されておらず、学校復帰への道を閉ざしてしまいますから決して適切な対応ではありません。
(2)「学校に問題はない、行きたいが行けない」という不登校は登校再開を目指すべき
このように不登校にもいろいろなタイプがあるのですが、文部科学省の実態調査の結果からも、様子を見ていても不登校が改善しないのは明らかですし、不登校のまま中学校を卒業することが好ましくないことも明らかです。また教育機会確保法の趣旨のように「学校以外の場所に本人の居場所を作ることを薦める」対応は、「学校に問題はない、行きたいが行けない」という形の不登校については完全に間違った対応といえます。
私たちは「学校に問題はない、行きたいが行けない」という形の不登校については積極的に登校再開を目指すべきであると考えています。当HP「パブリシティ紹介」の「灯台」でもお話ししているように、この形の不登校の原因のほとんどは「集団(学校)の中に居場所を作る力が十分に伸びていない」ことにあります。ですからこの形の不登校は「学校の中に居場所を作る力」を伸ばすことができれば比較的容易に登校できるようになるからです。
私たちの平成20年の調査でも「学校に問題はなく自分は学校に行きたい」という気持ちに間違いがなく、治療に取り組むことができれば、2~3ヶ月の治療期間で全体の67.6%までの患者さんは問題なく登校再開ができていました。多少の問題を残しながらも登校再開できたケースまでを含めれば登校再開率は97.2%に達します。2~3ヶ月でここまで改善するのであれば積極的に登校再開に挑戦することが好ましいといえます。
このような理由からきゅうとく医院では不登校については「早期に治療を開始し可能な限り早く改善に向かうことを目指す」ことが好ましいと考えています。早期に治療を開始することによりそれまで気づかれていなかった環境側の問題が「見えてくる」ことなどもあり、当面の治療方針が早期に決定できることになるからです。
そして環境(学校)側に大きな問題がある場合には進路変更なども考えますが、原則として元の学校に戻ることを前提とします。そして小中学校の不登校であれば中学校卒業までには登校を再開し普通卒業していくことを目指します。
(3)「居場所を作る力」は「生きるたくましさ」が伸ばしてくれる
きゅうとく医院では「居場所を作る力」を伸ばすための治療についておおむね次のように考えています。
ヒトは元々サルの仲間ですから「家族とか地域という大きな群の中で、時にはいざこざがあっても基本的には群れのメンバーが助け合って子どもを育てていく動物」です。ですからヒトの子どもが大人になった時には、「一人でも健全に生きていけること(生命維持)」、「群れを作ることができること(社会参加)」、「子供を育て上げて自立させること(健全な子育て)」の3つがまずは「自分なりに」できるようになっていなくてはなりません。
これらの3つの力が大人になってからの「生きるたくましさ」といえます。そしてこの「たくましさ」は生まれつき身についているものではなく、生まれてからの毎日の生活の中での経験を通して身につけていくものなのです。そして2番目の「群れを作る力」が「居場所を作る力」に相当します。ですからこの「居場所を作る力」の基礎である「生きるたくましさ」を伸ばすことができれば「学校の中に居場所を作る力(=登校する力)」も自然に伸びていくことになります。
「生きるたくましさ」といっても漠然としているように思われるかもしれませんが、私たちは「年齢相応に凛々しく頼もしく行動できる思考と行動の習慣」が備わった状態と考えています。
大人になるまでにその能力が身についていくように、現在の子どもたちの生活習慣を調整していくことがきゅうとく医院の不登校治療の基本になります。
「凛々しさと頼もしさ」を身につけていくための経験を通して子どもたちは自分が進む進路を模索して社会の中に自分の居場所を確立し、独り立ちしていくことができるように成長していきます。その結果として、自分が希望する居場所(学校とか社会)に自然に元気に胸を張って入っていく(不登校であれば登校を再開する)ことができるようになります。社会の中に居場所を作る力が伸びるのですから「8050問題」も当然発生しにくくなります。
反対にこの「居場所を作る力」が伸ばされることなく大人になった場合には、社会の中に居場所を作ることが難しくなり、成人後に社会不安障害、新型うつ、適応障害、などを発症する可能性が高まり、ひきこもりや「8050問題」に至る可能性も高まります。
このように考えてくると「居場所」は「与えられるもの」ではなく「自分で見つけ出してそこに参入する」か「自分で作り上げてそこで暮らす」ものということになります。
しかし現代の日本では子供も含めた若者たちの「健全な居場所」そのもの(私たちは「集団的生活環境」と呼んでいます)が衰退して「見つけ出しにくく、作り上げにくく」なっているいるという社会環境側の大きな問題があるのも事実です。この環境側の問題も不登校やひきこもり発生に強く影響を与えているのですが詳しい説明はここでは省略します。
以上のような考え方に基づき、きゅうとく医院では、不登校に対しては「登校を促すよりは本人に生きるたくましさが備わっていくように生活習慣を調整する」という方針の治療を行っています。
子どもたちに生きるたくましさが自然に備わっていくように、家族全体が共同して「毎日の生活習慣(=親子・家族の関わり方)」を健全な形に調整することが治療の第一歩になります。これを「健全生活の励行」と言います。そして健全生活の励行によって家族全体の生活習慣がたくましく健全な方向に変容していくことが治療そのものになるのです。
この治療法をきゅうとく医院では「生活療法」と呼んでいます。生活療法は認知行動療法の応用型と言えますが、不登校のみならず、適応障害、新型うつ、社会不安障害、職場ストレスによる休職、就労上のメンタルヘルス、ひきこもりなどの改善にも大きな効果があります。詳しくお知りになりたい方は当ホームページ、または参考書として「ここまで治せる不登校・ひきこもり」、「人間形成障害」などをご覧ください。
人間形成障害
この人間形成障害型の社会では、親がまったく普通の子育てをしているつもりであっても、子供たちに様々な問題が「予測もできない状況で自動的に」現れてくるようになります。
ぜんそくは自分で治せる
気管支ぜんそくの臨床は、いままでの『わからない・治らない』という時代から『原因を分析し実行すれば治る』時代に入ったのです...」。
ぜんそく根治療法
通院できない患者さんであっても、自宅で総合根本療法を実行して喘息を治していくことができるだけの知識を執筆されています。
ここまで治せる
不登校 ひきこもり
不登校をご家庭で「治す」ことも「予防する」ことも十分に可能です。不登校の解決は決して難しいものではないのです。